業務委託契約で収入印紙が必要な場合って?
公開日:2021.03.22
更新日:2025.03.24
業務委託契約を検討しており、収入印紙が必要なのか知りたい方向けに、収入印紙とは何か、収入印紙が必要になるケースと注意点について解説していきます。
本記事を読めば、業務委託契約で収入印紙が必要なのか、必要になる場合の金額が理解できます。
あなたの経験職種のフリーランス案件相場を確認しませんか?
<目次>
1.そもそも収入印紙とは
収入印紙とは
収入印紙を貼らないとどうなる?
印紙が必要な書面
2.業務委託契約の種類
委任(準委任)契約
請負契約
3.請負契約の収入印紙(2号文書)
4.継続性のある請負契約書の収入印紙(7号文書)
5.印紙の貼る時の注意点
印紙税の金額は契約内容によって変わる
印紙税の負担は双方
6.まとめ
1.そもそも収入印紙とは


業務委託契約で収入印紙が必要になるかを理解するためには、収入印紙について知る必要があります。
ここでは収入印紙について解説します。
収入印紙とは
収入印紙とは国に対する税金や手数料等の支払いを目的に発行される証票です。
収入印紙は印紙税法の課税文書を作成した場合に必要になります。
課税文書は業務委託契約書を含む20種類があります。
なお収入印紙はコンビニエンスストアで購入することが可能ですが、200円の額面の収入印紙のみを取り扱っていることが一般的です。
高額な収入印紙を購入する場合には、郵便局や法務局で購入しましょう。
名称が似ている証票に「収入証紙」があります。収入印紙と収入証紙は支払い先が異なります。
収入印紙は支払い先が国ですが、収入証紙は地方自治体が条例に基づいて発行しており、支払い先は地方自治体です。
なお東京都や広島県など、一部地方公共団体では廃止されています。
収入印紙を貼らないとどうなる?
収入印紙が貼られていない場合には、3種類のペナルティの中から状況に応じて1つのペナルティを受けます。
税務調査を受けた時に収入印紙が貼られていないことが発覚した場合には、最も重いペナルティが課せられ、当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されるため注意しましょう。
金額が大きい場合には、100万円を超える過怠税が発生してしまう可能性があります。
税務署調査を受ける前に自主的に不納付を申し出た際には、1.1倍に軽減されます。
収入印紙に消印しなかった場合には、消印されていない収入印紙の額面相当額の過怠税が徴収されます。
これらの過怠税は、法人税の損金や所得税の必要経費に算入されないため、注意が必要です。
ただ契約書に収入印紙を貼らなかったために、契約書の内容が無効になるといったことはありません。
契約書に収入印紙を貼らなかった場合には、印紙税法の違反とはなりますが法律に違反しているのは契約の内容ではなく、収入印紙を貼らなかったという行為です。
税金の申告漏れがあっても会社の取引が有効であるのと同様に、収入印紙を貼っていなかった場合でも契約書は無効にはなりません。
印紙が必要な書面
収入印紙は主に以下の書類に必要になります。
・5万円を超える金額の領収書
・一部の契約書(請負契約を含む)
・継続的取引の基本となる契約書
商品やサービスに対する金銭や有価証券の受領事実を証明する領収書には、金額が税抜きで5万円を超えた場合には、収入印紙が必要です。
あくまで本体価格が基準になることに注意しましょう。
例えば税込金額が5万2,800円の場合、本体価格は4万8,000円となり、収入印紙は必要ありません。
請負契約は受注者が受注した業務を完成させる対価として、発注者が報酬を支払うことを約束する契約です。
1万円未満の場合には収入印紙は必要ありませんが、1万円を超える場合には必要になります。
特定の相手と継続的に生じる取引の契約書には、一律で4,000円の収入印紙が必要です。
具体的には銀行取引契約書や代理店契約書、業務委託契約書が該当します。(契約内容により異なります)
2.業務委託契約の種類
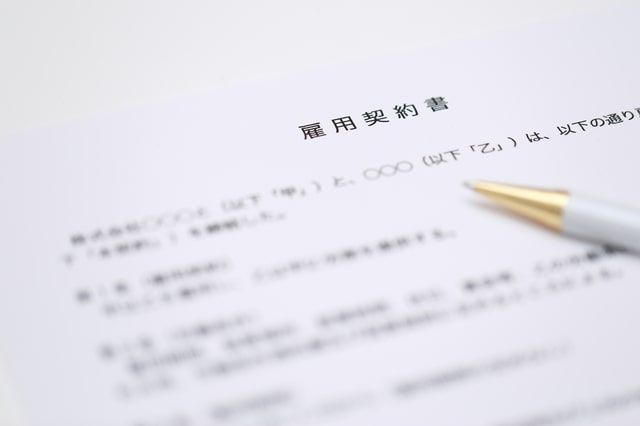
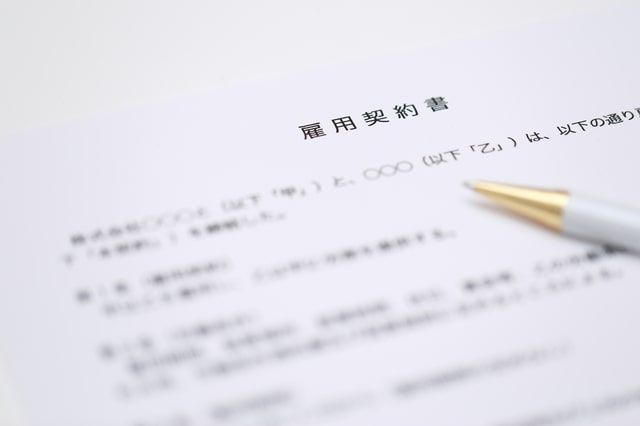
業務委託契約で収入印紙が必要な場合を理解するためには、業務委託契約の2つの主な種類について理解する必要があります。
委任(準委任)契約
委任(準委任)契約は業務の遂行を目的とする契約です。
後述の請負契約では成果や納品物に対価が支払われる一方で、委任契約では業務を行うことに対価が支払われます。
委任契約では善管注意義務が発生し、業務の遂行にあたって最新の注意を支払わなければなりません。
しかし「半年間顧問弁護士として在籍し、法律相談に乗る」といった委任契約を行なった場合、契約期間中に一度も法律相談を行う機会がなかった場合にも、対価を支払うことになります。
なお委任契約と準委任契約は民法上同一のルールが適用されるため、明確に区別せず、2つ合わせて委任契約と呼ばれるケースもありますが、厳密には委任契約と準委任契約は異なります。
委任契約は法律行為を委託する契約である一方、準委任契約は事実行為(事務処理)の委託を行います。
委任契約の例としては代理人契約が、準委任契約の例としてはセミナー講師としての講演、商品の宣伝業務など、さまざまな業務内容があげられます。
実際の取引においては準委任契約の方がより多く利用される契約です。
請負契約
請負契約は業務の結果を目的とする契約を指します。
委任契約との大きな違いは、委任契約は業務を行うことに対価を支払う契約のため、成果や納品物をあげなくても対価を得られますが、請負契約では成果や納品物をあげなければ対価が発生しないことです。
例えばデザイナーに商品のパッケージデザインを依頼する場合に、デザイナーは納期までにデザインを納品してはじめて、対価が発生します。
またある期間内に一定額の売上を上げるといった営業代行も請負契約が適しています。
事前に報酬を決めず、売上の一部を報酬として支払うといった契約も請負契約では可能です。
3.請負契約の収入印紙(2号文書)


請負契約は「請負に関する契約書(2号文書)」と呼ばれ、契約金額に応じて収入印紙の貼り付けが必要です。
請負契約金額ごとの必要な収入印紙の金額は、以下のようになっています。
| 契約金額ごとの必要な収入印紙 | |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え300万円以下 | 1千円 |
| 300万円を超え500万円以下 | 2千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
| 1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 |
| 契約金額の記載がないもの | 200円 |
4.継続性のある請負契約書の収入印紙(7号文書)


請負基本契約書や業務委託基本契約書(請負)、売買基本契約書、代理店契約書、販売代理店契約書、取引基本契約書、業務委託契約書(請負)などの継続的取引が基本となり、契約金額の記載のない契約書は第7号文書と呼ばれ、一律で4000円の印紙が必要になります。
なお契約期間が3ヶ月以内で、更新の定めのないものは除きます。
5.印紙の貼る時の注意点


印紙を貼る際には、以下の2つの注意点があります。
理解していないと、過怠税の支払いを行わなければならなくなる恐れもあります。
印紙税の金額は契約内容によって変わる
印紙税の金額は契約内容によって変わります。
業務委託契約のうち、委任契約は基本的に収入印紙は不要です。
しかし7号文書に当たる委任契約には、収入印紙が必要になります。金額は一律で4,000円です。
また2号文書に当たる請負契約の場合には、契約金額に応じて無課税〜60万円の幅で変動します。
印紙税の負担は双方
印紙税は双方が負担するのが一般的です。
印紙税法では契約書の作成者はこれを支払う義務を負うと決められています。
また当事者が連帯して印紙代を負担することが定められており、連帯納税義務があるため、双方ともに負担することが多いです。
しかし印紙税法では負担割合は定められていないため、当事者同士で合意し、決定します。
6.まとめ
業務委託契約は委任(準委任)契約と請負契約に大きく分けられます。
委任(準委任)契約は7号文書の場合を除いて、収入印紙は必要ありません。
一方で7号文書の委任(準委任)契約の場合と請負契約の場合には収入印紙が必要になります。
フリーランスエンジニア専門の求人・案件一括検索サイト「フリーランススタート」に少しでも興味がある方は是非ご登録ください。
なお、フリーランススタートはiOSアプリ版やAndroid版をリリースしています。
通勤しているエンジニア・デザイナーでちょっとしたスキマ時間で手軽にフリーランス求人・案件を検索したい、開発言語の単価が知りたい、フリーランスを将来的に検討している方などは是非インストールしてみてください。
フリーランススタートのアプリを有効活用して、フリーランスとして第一線で活躍しましょう!
フリーランススタート iOSアプリのインストールはこちらから→
フリーランススタート Androidアプリのインストールはこちらから→
本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。
フリーランスお役立ち記事を検索
新着のフリーランス向けお役立ち記事
おすすめのフリーランス向けお役立ち記事
あなたの経験職種のフリーランス案件を見てみませんか?













SNSアカウントでログイン